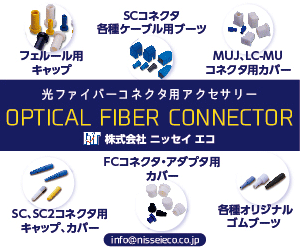TelstraとEricssonが、自律型ネットワークの未来を形作るためのコラボレーション プログラムを開始
海外TOPICS 有料Ericssonは10月7日、TelstraとEricssonが協力して自律型ネットワークへの移行を加速させる枠組みを提供することにフォーカスした、先進的な契約を締結したと発表した。
Ericssonは「通信業界は自律性の加速を急務としているが、完全な自律ネットワークへの道筋は依然として複雑だ。このビジョンを実現するには、技術面と運用面の障壁を克服し、標準規格に準拠する必要がある。業界全体にわたる協業、イノベーション、そしてオープン性が求められる」と説明している。
この記事は会員限定です。新規登録いただくか、会員の方はログインして続きをお読みください。
更新