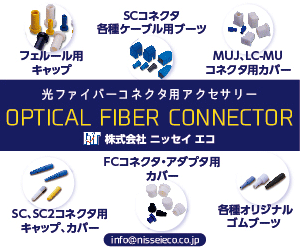NscaleがMicrosoftと約20万基のNVIDIA GB300 GPUを契約し、欧州および米国全域にNVIDIA AIインフラストラクチャを提供
海外TOPICS 有料Nscaleは10月15日(ロンドン)、Microsoftとの契約拡として、欧州と米国に約20万基のNVIDIA GB300 GPUを導入するハイパースケールNVIDIA AIインフラストラクチャの契約を発表した。
Nscaleは「これは過去最大規模のAIインフラストラクチャ契約の一つとなる。この契約はDell Technologiesとの共同作業だ」と説明している。
この記事は会員限定です。新規登録いただくか、会員の方はログインして続きをお読みください。
更新