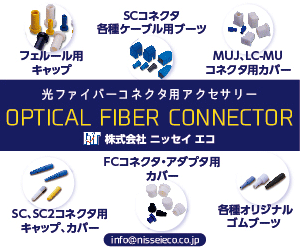FOEセミナー企画委員インタビュー:鈴木 巨生氏【三菱電機】FOE-5
INTERVIEW 有料(期間限定無料公開中)
■講演タイトル
【FOE-5】
Space Compassが目指すマルチオービット構想と宇宙光通信技術の最新動向
■コースリーダー
三菱電機
インフラBA 通信システムエンジニアリングセンター
エンジニアリング推進室長
鈴木 巨生
■講演者
Space Compass
宇宙DC事業部
上席技術主幹
荒木 智宏

三菱電機
インフラBA 通信システムエンジニアリングセンター
エンジニアリング推進室長
鈴木 巨生氏
Space Compassは、宇宙光通信技術を最大限に活用し、HAPS~LEO~GEOそれぞれの軌道(オービット)特性を組み合わせたマルチオービットNTN、さらに宇宙データセンタ(DC)を実現することをめざしている。本講演では、キー技術である宇宙光通信技術について、特に高精度捕捉追尾技術に焦点を当てて解説される。併せて海外の動向も概説される。
コースリーダーを務める鈴木氏は「光ファイバ通信で使われてきた光技術は、様々な分野で応用が進んでいる。その中で、今後の期待値の高い分野の一つが宇宙通信だ。宇宙通信は大容量化が進むので光技術と親和性があり、例えばデジタルコヒーレントは軌道間や地上間を結ぶ高速、高信頼の通信を実現するための中核技術として注目されている。また宇宙光通信は標準化も整いつつあるので、グローバルのビジネスという規模感も期待できる」とし、「ただ、現時点では、日本の宇宙光通信はまだ研究、実証フェーズ寄りであり、本格的な市場や商用サービスの立ち上がりとしては、これからとなる。今後、光通信の技術やコミュニティをお持ちの多くの企業の力が、宇宙の光技術を盛り上げることで、事業機会が生まれてくるだろう。今は、宇宙光通信のビジネスを見定めている段階という方も多いと思うので、本講演で最新の動向をお伝えすることで、ビジネスの判断のお役に立てればと考えている」と話す。
宇宙通信において、海外は主にLEO通信サービスの商用化に集中しており、複数の軌道の統合に地上ネットワーク連携まで含めた全体構想はSpace Compassが突出している。シンプルな構成かつ実用化段階にあるLEO通信に対し、マルチオービットは複雑な構成となるが、宇宙通信の高度化により宇宙産業全体の発展を促すことで、新たな雇用創出や技術革新に繋がる将来の拡張性のある構想であり、LEO通信の次の段階として、日本が国際競争力を発揮できる領域と言える。また、複数の軌道を使うことで災害時の通信インフラの安定性も強化されるので、国民の安全や生活基盤を守る国策とも相性が良い。
登壇する荒木氏は、1992年に宇宙開発事業団(現:宇宙航空研究開発機構(JAXA))入社。 長年に渡り宇宙光通信の研究開発に従事。光衛星間通信実験衛星(OICETS, 「きらり」)プロジェクト立上げ業務、光データ中継システム(LUCAS)開発運用支援などを経験。 2000年~2001年に欧州宇宙機構(ESA)技術センター(ESTEC) 交換研究員。 2013年~2023年、宇宙データシステム諮問委員会(CCSDS)の光通信WGにJAXA代表として参加。欧州滞在およびCCSDS活動により欧米の宇宙機関、関連企業での宇宙光通信の状況に詳しい。 2025年~、(株)Space Compass上席技術主幹。宇宙光通信を中心とした衛星技術の評価、研究開発プロジェクト等に従事。
鈴木氏は「荒木氏は超長距離の光通信に必要な高速追尾やハイパワーアンプにも精通しており、日本における宇宙光通信の技術体系の構築に寄与してきた人物だ。本講演では、現状の宇宙光通信の取り組みということで、マルチオービットを支える中核技術の一つである、異なる軌道間での超長距離光通信を実現するために必要な高精度捕捉追尾技術についても詳細を解説していただく」と話している。
宇宙向けの光通信インフラのビジネスは、地上向けに比べて数量のボリュームは小さいものの、高信頼性や超小型、低消費電力といった付加価値を活かした利益率が注目されている。光通信の歴史を振り返れば、日本は世界に先駆けて光ファイバ網を全国整備した国であり、それを支える高信頼、高品質な光機器や光デバイスを供給してきたベンダの企業文化は、マルチオービットに求められる安定性、精度、柔軟性においても強みとなる。技術志向の地道な積み上げを、宇宙光通信というハイエンド市場で活かせるかどうかを考える時、高精度捕捉追尾技術をはじめとする宇宙光通信の最新動向から感じ取る光技術の要件が役に立つだろう。
(OPTCOM編集部)
FOEセミナー企画委員インタビュー目次
■7月30日(水)の講演
【FOE-1】AIクラスター向け光インターコネクト:2025年、そしてその先へ
企画委員:小熊 健史氏【日本電気】
【FOE-2】空孔コアファイバ(Hollow-Core Fiber)の次世代光通信応用
企画委員:黒部 立郎氏【古河電気工業】
■7月31日(木)の講演
【FOE-3】先進アドバンスト・パッケージング、チップレット、フォトニクスおよび電気ダイの統合に関するケーススタディ
企画委員:才田 隆志氏【NTT】
【FOE-4】光電融合時代の光通信を支える超広帯域光増幅技術
企画委員:玉置 忍氏【住友電気工業】
【FOE-5】Space Compassが目指すマルチオービット構想と宇宙光通信技術の最新動向
企画委員:鈴木 巨生氏【三菱電機】
【FOE-6】224GbpsのSERDESとI/O、PAM4と448Gbpsへの道
企画委員:山中 正樹氏【キーサイト・テクノロジー】
【FOE-7】IOWN におけるAll Photonics Network の最新研究開発動向
企画委員:柳 秀一氏【NTT アドバンステクノロジ】
■8月1日(金)の講演
【FOE-8】AIデータセンタ構築に向けたLLM/GPUと光回線の最新技術動向
企画委員:和田 悟氏【フジクラ】
【FOE-9】異種材料集積技術の最新動向
企画委員:黒部 立郎氏【古河電気工業】
【FOE-10】AI時代を支える光トランシーバの最新動向
企画委員:布施 由起治氏【古河ファイテルオプティカルコンポーネンツ】
【FOE-11】既設通信光ファイバを用いた光ファイバセンシング基盤の実現に向けて
企画委員:森 浩氏【アンリツ】