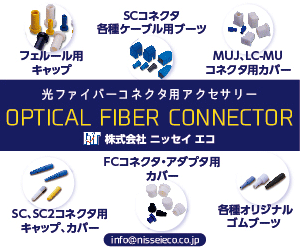FOEセミナー企画委員インタビュー:布施 由起治氏【古河ファイテルオプティカルコンポーネンツ】FOE-10
INTERVIEW 有料(期間限定無料公開中)
■コースタイトル
【FOE-10】
AI時代を支える光トランシーバの最新動向
■コースリーダー
古河ファイテルオプティカルコンポーネンツ
執行役員
布施 由起治

古河ファイテルオプティカルコンポーネンツ
執行役員
布施 由起治氏
AIの発展により、ネットワークに対する需要はどのように変化していくのか。それを光トランシーバに対する需要や要求から読み解いていくのが、本コースのアプローチだ。
AI処理では非常に大量のデータが扱われ、クラスタ間通信のトラフィックは急増し、推論サービスやエッジAIでは、リアルタイム性・低遅延・高信頼の要求が増大する。このようなAIの発展がネットワークに与える影響は、データセンタの限られた空間における、大量の高速接続、低遅延、低電力という要求で現れており、その進捗や今後のニーズは光トランシーバの動向と一致しているので、データセンタの中で何が起きているかを知る最良の手がかりの一つが光トランシーバと言えるだろう。
コースリーダーを務める布施氏は「本コースは3つの講演をプログラムしており、冒頭は中国におけるデータセンタの技術動向や市場動向に関する講演となる。これまでAIの領域では北米が注目されていたが、DeepSeekの例もあり中国の注目度が高まっている。また、北米と中国はモデルの性能競争だけでなく、例えば自動車やスマートシティなど産業連携などが大きく異なり、同じLLMでも目的が違う状況になってきているので、中国のAIデータセンタの現状を光トランシーバ需要の観点から読み解く本講演は、北米との違いを整理する上でも非常に役立つだろう」としており、「続く二つの講演では、データセンタの短距離、そして長距離をテーマとした。それぞれ高速化が進む中で、800Gの状況や、1.6T、3.2Tの展望はどのようなものなのかを扱う。私としても興味深い項目が多く、例えば、コヒーレントは長距離のイメージだが、800G、1.6T、3.2Tと高速化するにつれて、より短距離でもコヒーレントが求められる傾向が強くなる。また、AI需要によるトラフィック増でC/L-bandの逼迫が懸念されていることから、O-bandのコヒーレント研究も進んでいる。市場予測では、プラガブルとコパッケージの注目度は高い。材料系では、シリコンフォトニクス、InP、薄膜LNの考察もある。こうした技術動向や業界動向をお伝えすることで、AI時代のビジネスのお役に立てればと考えている」と話す。
■講演タイトル
AI時代における短距離光インターコネクションの開発動向と要件
■講演者
Huawei Technologies
Optoelectronics business Dept, Technical expert
Cao Pan
高速光インターコネクションの需要は、AIコンピューティングパワーの急増に後押しされて急速に高まっている。現在、800GEソリューションが大規模に展開されており、1.6T技術は急速に商用化に向かっている。
一方、ショートリーチの光相互接続技術は急速にアップグレードが進んでいる。シングルモードシリコンフォトニクスは200G/レーンを超え、EML/TFLN技術は次世代の400G/レーンに向けて前進し、マルチモード224G VCSEL技術は絶えず限界を押し広げている。2025年までには、商業的に大きなブレークスルーが見込まれている。
さらに、LPO、LRO、OBO、CPOなど、消費電力が低い光相互接続ソリューションが、商業的な実現可能性を積極的に探っている。その結果、短リーチ光モジュールの今後の需要は増加し、多様化すると予想される。
登壇するCao Pan氏は、2014年に中国の上海交通大学で電気工学(EE)の博士号を取得。卒業後、華為(Huawei)のオプトエレクトロニクス事業部に技術スタッフとして入社。現在は、オプトエレクトロニクス事業部の技術専門家として、次世代の光チップおよび光モジュール技術を担当。ここ数年で、100Gbaud EML、100Gbaud以上のシリコンモジュレーター、100Gbaud VCSELを含む革新システムの応用に貢献。学術誌や内部会議で30件以上の論文を発表しており、10件以上の中国特許を保有している。
■講演タイトル
クラウドデータセンタAIクラスタ向け超高速Pluggable光トランシーバの最新動向
■講演者
CIG Photonics Japan
マーケティング部
統括部長
平本 清久
ChatGPT等の生成系AIの適用が全世界的な広まりを見せる中、データセンタ内のAIクラスタでは800Gbpsおよび1.6Tbps光トランシーバの適用が急速に進む見通しであり、さらに3.2Tbps光トランシーバの実現に向けた光部品の開発が本格化している。本講演では、光トランシーバの最新動向をIEEEにおける次世代イーサネット光インターフェースの規格化および光トランシーバの方式・フォームファクタの最新のトレンドの観点から概観する。
登壇する平本氏は、1991年3月東北大学院理学研究科卒業、1991年4月日立製作所中央研究所入所。その後日本オプネクスト、日本オクラロ、Lumentumを経て、現在はCIG Photonics Japanに所属。光トランシーバのマーケティングを担当、XFP, CFP, PSM4, CWDM4等のMSAやIEEE等の標準化会合活動へ参画。現在は主に800Gbps超級の次世代光トランシーバの製品企画およびマーケティングに従事。
■講演タイトル
次世代コヒーレント光トランシーバーの最新動向と今後の展望
■講演者
古河ファイテルオプティカルコンポーネンツ
OC事業部 開発エンジニア
長瀬 竜嗣
光トランシーバはトラフィックの拡大が続く大容量光ネットワークを支えるため進化を続けている。特にデータセンタ間を結ぶ80kmを超えるような比較的長距離伝送においてはデジタルコヒーレント技術を使用した光トランシーバが重要な役割を果たしており、近年では短距離通信においてもコヒーレント光トランシーバの活用が進んでいる。本講演ではこのようなコヒーレント光技術に関する最新状況と技術動向について説明する。
登壇する長瀬氏は、2006年3月大阪大学大学院卒業後(修士)、同年4月富士通入社。光モジュール事業本部に所属して光デバイス開発と10Gクライアントモジュールの開発に従事。 2009年4月より富士通オプティカルコンポーネンツ(FOC)に所属して主にCFP2-ACOの開発を担当し、その後2017年1月より米国に駐在してFAE、マーケティングに従事。 2021年7月より帰国して400ZR/OpenZR+モジュール、800ZR/ZR+モジュールの開発リーダーを担当。2025年4月より古河ファイテルオプティカルコンポーネンツに所属して現在に至る。
(OPTCOM編集部)
FOEセミナー企画委員インタビュー目次
■7月30日(水)の講演
【FOE-1】AIクラスター向け光インターコネクト:2025年、そしてその先へ
企画委員:小熊 健史氏【日本電気】
【FOE-2】空孔コアファイバ(Hollow-Core Fiber)の次世代光通信応用
企画委員:黒部 立郎氏【古河電気工業】
■7月31日(木)の講演
【FOE-3】先進アドバンスト・パッケージング、チップレット、フォトニクスおよび電気ダイの統合に関するケーススタディ
企画委員:才田 隆志氏【NTT】
【FOE-4】光電融合時代の光通信を支える超広帯域光増幅技術
企画委員:玉置 忍氏【住友電気工業】
【FOE-5】Space Compassが目指すマルチオービット構想と宇宙光通信技術の最新動向
企画委員:鈴木 巨生氏【三菱電機】
【FOE-6】224GbpsのSERDESとI/O、PAM4と448Gbpsへの道
企画委員:山中 正樹氏【キーサイト・テクノロジー】
【FOE-7】IOWN におけるAll Photonics Network の最新研究開発動向
企画委員:柳 秀一氏【NTT アドバンステクノロジ】
■8月1日(金)の講演
【FOE-8】AIデータセンタ構築に向けたLLM/GPUと光回線の最新技術動向
企画委員:和田 悟氏【フジクラ】
【FOE-9】異種材料集積技術の最新動向
企画委員:黒部 立郎氏【古河電気工業】
【FOE-10】AI時代を支える光トランシーバの最新動向
企画委員:布施 由起治氏【古河ファイテルオプティカルコンポーネンツ】
【FOE-11】既設通信光ファイバを用いた光ファイバセンシング基盤の実現に向けて
企画委員:森 浩氏【アンリツ】