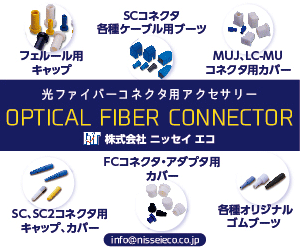FOEセミナー企画委員インタビュー:才田 隆志氏【NTT】FOE-3
INTERVIEW 有料期間限定無料公開中
■講演タイトル
【FOE-3】
先進アドバンスト・パッケージング、チップレット、フォトニクスおよび電気ダイの統合に関するケーススタディ
■コースリーダー
NTT
IOWN総合イノベーションセンタ
デバイスイノベーションセンタ
センタ長
才田 隆志
■講演者
Advanced Micro Devices Inc.
Global Operations and Quality, Senior Fellow, Technology and Product Engineering
Matt Klein

NTT
IOWN総合イノベーションセンタ
デバイスイノベーションセンタ
センタ長
才田 隆志氏
AMDは、システム最適化を目的としてチップレットを活用した先進パッケージング技術を追求しており、10年以上にわたり最先端技術の推進に取り組んでいる。これらのシステムは、モノリシックダイ(単一チップ)からMCM(マルチチップモジュール)、さらに高性能かつ電力効率に優れた高度な接続性を備えた3Dシステムへと進化してきた。本講演では、AMDが取り組んできた先端パッケージ技術と、電気と光の両方の技術を組み合わせた総合アーキテクチャの設計と評価が紹介される。
コースリーダーを務める才田氏は「これまで光電融合に関する講演では光技術側の視点から語られることが多かったが、光技術を半導体のエコシステムに導入していく上で、半導体からの視点で光技術を語ることも重要である。そこで今回の講演では、AMDから最先端のパッケージ技術とその応用事例を紹介してもらい、特に、電気と光の融合による事例も紹介してもらうことで、インターフェース設計の実際に迫ってもらう内容にする」と話している。
光電融合はIOWN構想における中核技術の一つであると同時に、通信市場で培ってきた光技術を巨大な半導体市場で活用する機会でもある。また、AMD、そしてNVIDIAやBroadcomのCPOへの取り組みの進捗など、実用化への期待が高まるニュースが次々と発表されている。光電融合というブレイクスルーの実現が見えてきた今、本講演の魅力は、最先端の研究動向を知ることができる点はもちろん、光電融合が半導体市場に与えるインパクト規模を予測するのに役立つ点も挙げられる。AI・HPCなどの次世代アプリケーションには、広帯域・低消費電力なインターフェースが求められている。そうした中で光電融合は期待されている技術だが、市場を予測する上では電気側からのシステム設計的な視点は欠かせない。本講演で語られる光電融合の話は、光通信側が語る光技術の魅力とは異なるアプローチであり、実装制約、費用対効果、システム最適性をふまえた半導体の実務者の声となる。AMDから見た光電融合のケーススタディは、どのような技術連携が可能なのかを具体的に示す最新事例として非常に価値があり、聴講者にとっては光電融合が切り拓く市場に対する研究開発や事業計画のロードマップを描く上で有益な情報となるだろう。
才田氏は「AMDはGPUやXPUの領域での主要プレイヤーであり、我々もロジックICのメインプレイヤーとして非常に重要なパートナーだと認識している。また、オープン規格にも積極的に参加されているので、企業としての戦略や哲学は、同じくオープンを掲げるIOWN構想と非常に近いと感じている。光電融合のような次世代の基盤技術においては、オープンな規格やエコシステムがさらなる成長のドライバになるだろう」と話している。
登壇するマット・クライン氏は、AMDのシニアフェローであり、Xilinxの在籍期間を含め、通算21年間にわたりAMDに在籍している。
ケース・ウェスタン・リザーブ大学で電気工学士号(BSEE)を、サンタクララ大学で電気工学修士号(MSEE)を取得しており、エンジニアとしてのキャリアは41年に及ぶ。1984年にヒューレット・パッカードのRFおよびマイクロ波部門でキャリアをスタートし、初期のFPGA活用における先駆者でもある。
現在は、AMDのグローバルオペレーションおよび品質部門におけるテクノロジー&プロダクトエンジニアリング部門に所属している。これまでに、AMDおよびXilinxにおいて、製造、技術マーケティング、アプリケーションなどの分野でも役職を歴任し、常にフィールド組織や顧客との密接な連携を重視して業務に取り組んでいる。
才田氏は「最先端技術に携わるマット氏から成果や課題を示していただくことで、光と電気の棲み分けや協力できる領域が見えてくると思う。これは光通信分野の方々だけでなく、半導体分野の方々にとっても有益な情報となる。今年のFOEセミナーでは電気SERDESを扱うコースや、シリコンフォトニクスの異種材料集積を扱うコースもプログラムしているので、そうした講演と併せてご聴講いただくことで、多面的な視点で理解を深めていただけるだろう」と話している。
(OPTCOM編集部)
FOEセミナー企画委員インタビュー目次
■7月30日(水)の講演
【FOE-1】AIクラスター向け光インターコネクト:2025年、そしてその先へ
企画委員:小熊 健史氏【日本電気】
【FOE-2】空孔コアファイバ(Hollow-Core Fiber)の次世代光通信応用
企画委員:黒部 立郎氏【古河電気工業】
■7月31日(木)の講演
【FOE-3】先進アドバンスト・パッケージング、チップレット、フォトニクスおよび電気ダイの統合に関するケーススタディ
企画委員:才田 隆志氏【NTT】
【FOE-4】光電融合時代の光通信を支える超広帯域光増幅技術
企画委員:玉置 忍氏【住友電気工業】
【FOE-5】Space Compassが目指すマルチオービット構想と宇宙光通信技術の最新動向
企画委員:鈴木 巨生氏【三菱電機】
【FOE-6】224GbpsのSERDESとI/O、PAM4と448Gbpsへの道
企画委員:山中 正樹氏【キーサイト・テクノロジー】
【FOE-7】IOWN におけるAll Photonics Network の最新研究開発動向
企画委員:柳 秀一氏【NTT アドバンステクノロジ】
■8月1日(金)の講演
【FOE-8】AIデータセンタ構築に向けたLLM/GPUと光回線の最新技術動向
企画委員:和田 悟氏【フジクラ】
【FOE-9】異種材料集積技術の最新動向
企画委員:黒部 立郎氏【古河電気工業】
【FOE-10】AI時代を支える光トランシーバの最新動向
企画委員:布施 由起治氏【古河ファイテルオプティカルコンポーネンツ】
【FOE-11】既設通信光ファイバを用いた光ファイバセンシング基盤の実現に向けて
企画委員:森 浩氏【アンリツ】